夫婦喧嘩が繰り返される理由を構造的に読み解く

- 暴力などで困っている方はこちらを参照下さい
-
1. こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)
心の悩みや不安を抱えたときに、全国どこからでも利用できる相談窓口です。
電話をかけると、地域の精神保健福祉センターや保健所につながり、専門スタッフが対応してくれます。
👉 厚生労働省公式ページ2. よりそいホットライン(0120-279-338)
24時間365日、無料で誰でも利用できる相談窓口です。
夫婦関係や家庭の悩みだけでなく、生活・仕事・人間関係など幅広く対応。
電話・チャット・SNSでも相談可能で、匿名で利用できます。
👉 よりそいホットライン公式サイト3. DV相談ナビ(#8008)
固定電話や携帯電話から「#8008」を押すと、発信地に応じた最寄りの「配偶者暴力相談支援センター」につながります。
DVやモラハラなど、安全に関わることに悩んだときに利用できる全国共通の窓口です。
👉 DV相談ナビ(内閣府 男女共同参画局)4. DV相談+(プラス)(0120-279-889)
電話・チャット・SNSで24時間365日相談可能な窓口です。
匿名でDVやモラハラ、強い不安を抱える人が気軽に利用できます。
👉 DV相談+(プラス)公式サイト5. 女性相談支援センター(#8778)
全国の「女性相談支援センター」につながる共通番号です。
夫婦関係、家庭、生活の悩みなど、幅広いテーマを無料で相談できます。
👉 女性相談支援センター案内(厚生労働省)⚖️ 男性の方へ
全国統一の「男性相談」専用窓口はまだ整備されていません。
ただし、多くの自治体の男女共同参画センターでは「男性のための相談」が設けられています。
「地域名 + 男性相談」で検索すると、お住まいの地域の窓口が見つけやすいです。
.jpg)
結婚してからというものずっと喧嘩している気がする
ずっとこのまま生きていかないといけないのかな…
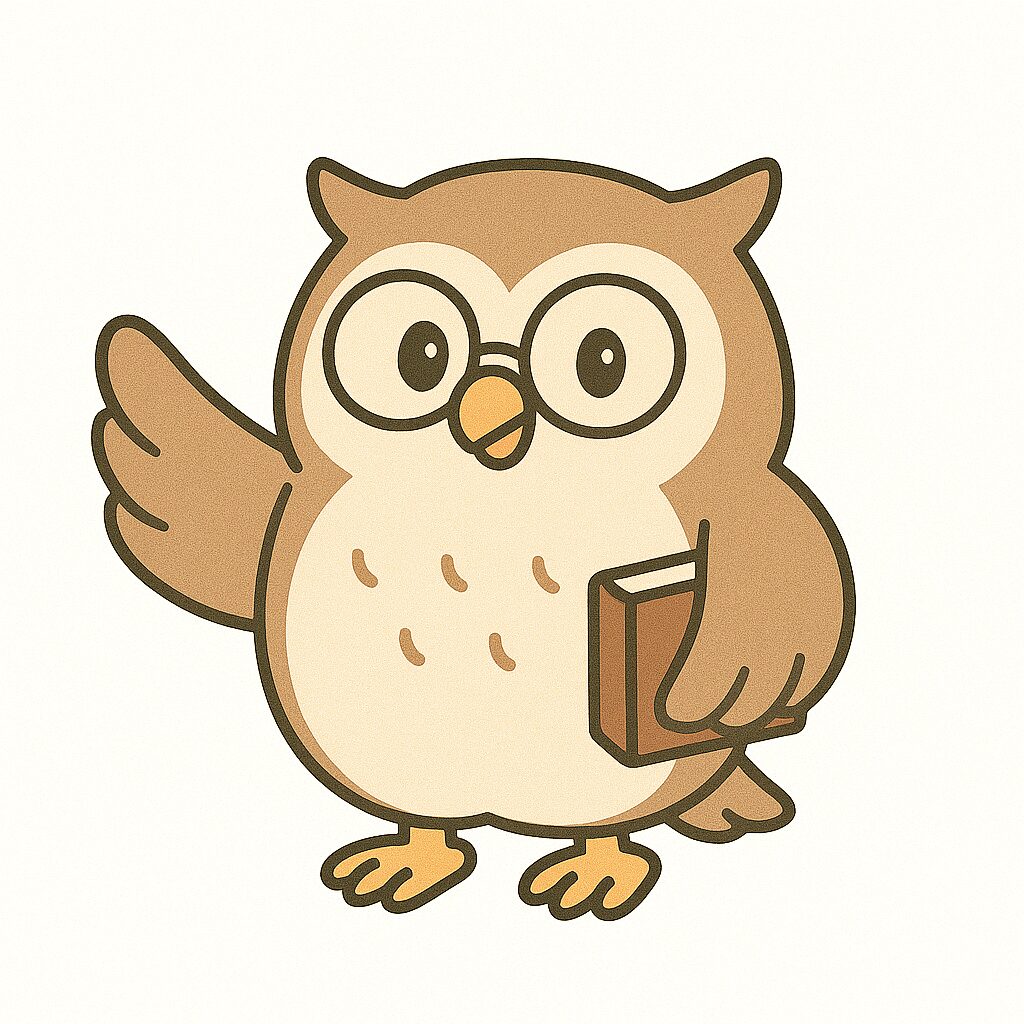
それはつらいね
今回は夫婦喧嘩が起こる原因と、解決策を話していくよ
夫婦の会話の中で、「どうして同じことで何度も言い合いになってしまうのだろう…」と感じたことはありませんか? 一度は収まったはずなのに、また同じテーマで火がつき、繰り返すように喧嘩になる——。これは多くの夫婦が抱える共通の悩みです。
なぜ喧嘩が繰り返されるのか? その背景には、表面的な原因に加え、発達段階の違いによるものの見方、さらには心理的なループが関わっています。そして大切なのは、それらを理解したうえで「相手に合った関わり方」を工夫することです。
本記事では、成人発達理論を手がかりに、夫婦喧嘩が繰り返される理由を整理し、そのループを断ち切るための具体的な実践法を紹介します。
この記事で分かること
- 夫婦喧嘩が繰り返される 3つの典型的な原因
- 喧嘩の背後には、成人発達理論における発達段階の特徴
- 夫婦喧嘩を繰り返す背景にある 心理的ループ
- 発達段階と心理ループを踏まえた、段階ごとの実践的な対処法
🍀 夫婦喧嘩の3大原因
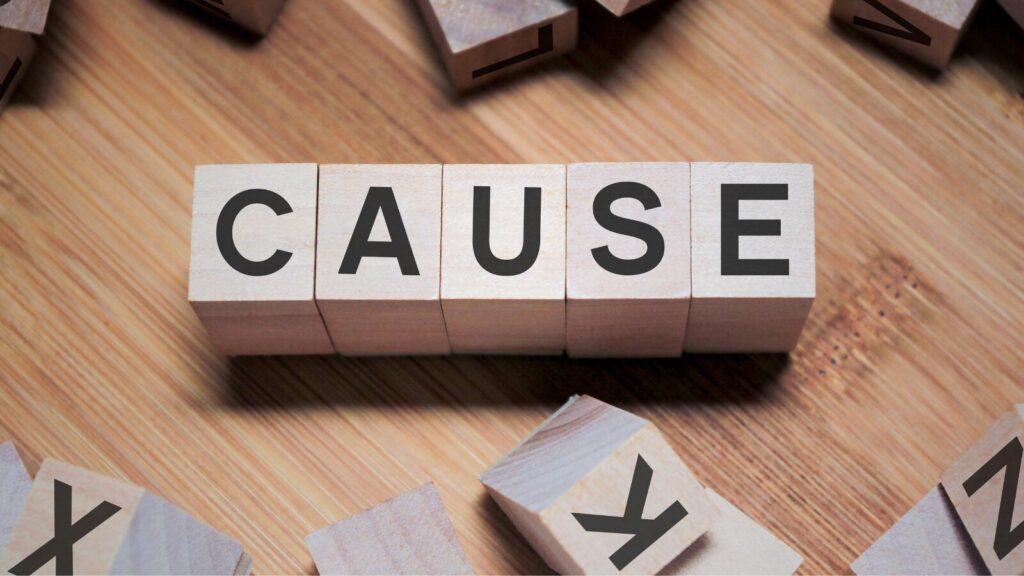
夫婦喧嘩が繰り返される背景には、いくつかの典型的な原因があります。表面的には「ちょっとした言い合い」に見えても、その奥には深い構造が隠れています。ここでは特に多い3つのパターンを紹介します。
1. 価値観の不一致
育った環境や人生経験の違いから、夫婦はそれぞれ異なる価値観を持っています。「お金の使い方」「子育ての方針」「休日の過ごし方」など、日常の小さな選択の中にも価値観の違いが現れます。初めのうちは妥協できても、積み重なると「どうして分かってくれないの?」という思いに発展しやすいのです。
2. 役割期待のズレ
夫婦の間には暗黙の「役割分担」に対する期待があります。「家事はどちらが多くするのか」「仕事と家庭の優先順位をどうするのか」など、その期待がずれると「私はこれだけやっているのに…」という不満が生まれます。このズレは、本人同士が気づきにくいために繰り返されやすいのが特徴です。
3. 感情処理の違い
怒りや不安などの感情をどう扱うかは、人によって大きく異なります。ある人は「すぐに話して解消したい」と思い、別の人は「一人で落ち着いてから話したい」と考える。こうした感情処理スタイルの違いが、すれ違いを増幅させてしまいます。結果的に「同じテーマで何度もぶつかる」という現象が起きるのです。
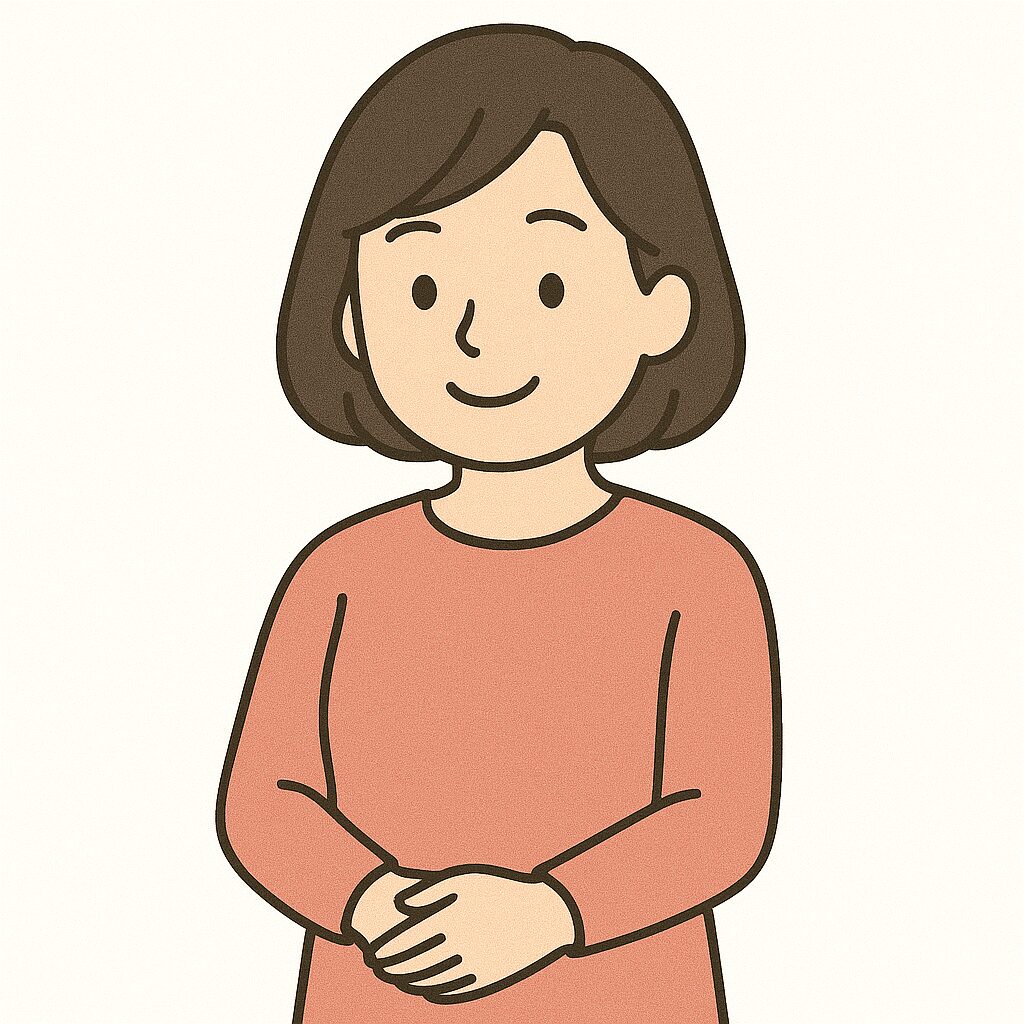
夫婦喧嘩の原因って、価値観や役割、感情の違いにあったんですね。
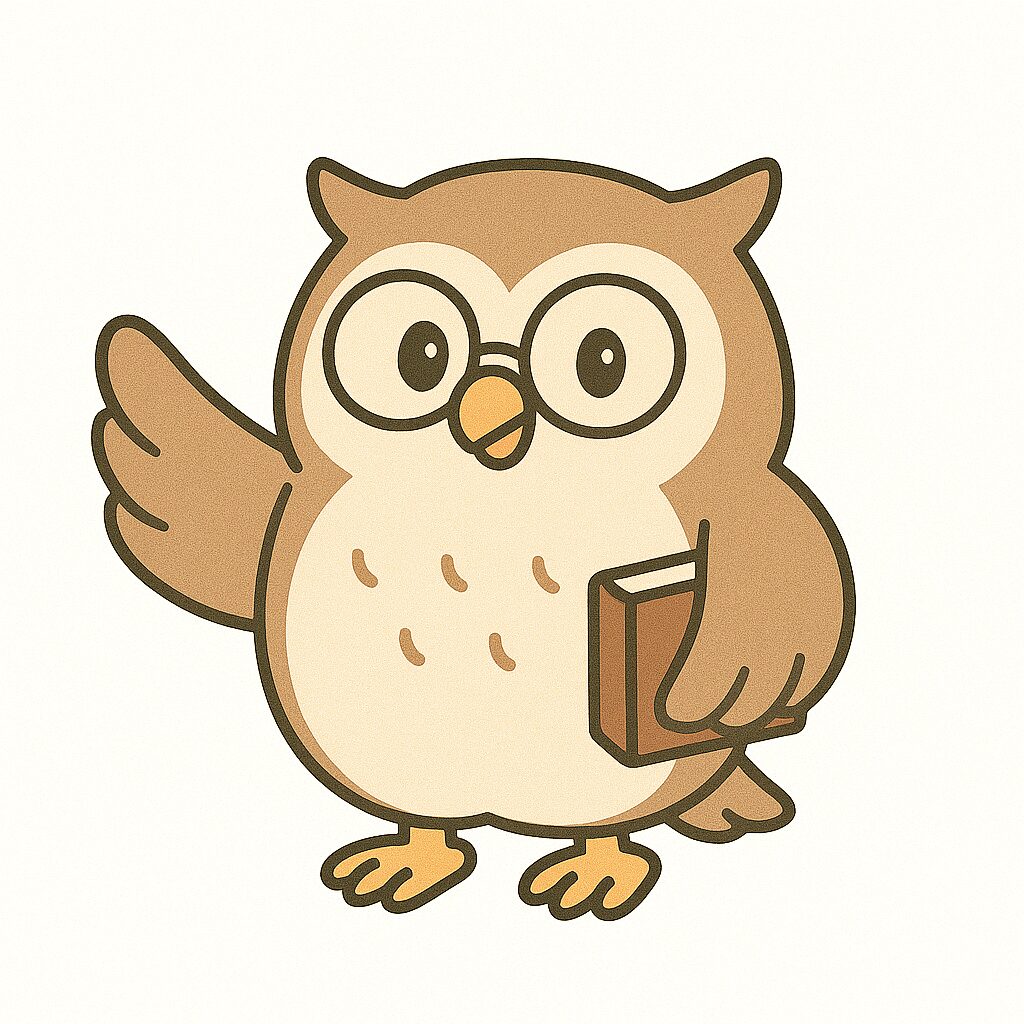
そうです。そして同じ原因でも、人の発達段階によって受け止め方や反応は変わります。次はその違いを見ていきましょう。
🍀 発達段階別の争いパターン
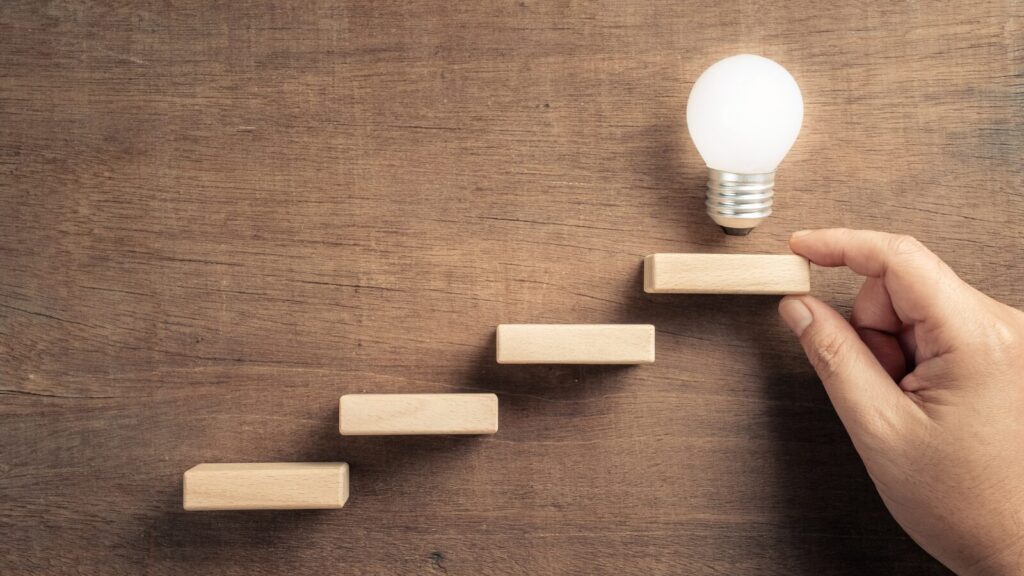
ロバート・キーガンが提唱した成人発達理論によると、人の思考や人間関係のあり方は、発達段階によって特徴が異なります。夫婦喧嘩においても、「価値観の不一致」「役割期待のズレ」「感情処理の違い」といった原因は、それぞれ段階的な傾向と結びついています。
1. 第二段階 ― 自己保身型(他人を道具として扱うタイプ)
この段階では、自分の欲求や利益を最優先にし、相手を「自分の都合に合わせるべき存在」と見てしまう傾向があります。
- 価値観の不一致:自分の損得に合わない価値観を受け入れにくく、「自分の言うことを聞くのが当然」となりがち。
- 役割期待のズレ:家事や家庭の役割も「やってもらって当たり前」と考え、不満を募らせやすい。
- 感情処理の違い:不満を抑えられず爆発し、喧嘩を繰り返す。
👉 結果として、思い通りにならないと怒り、支配的な関わり方で争いが再生産されやすくなります。
2. 第三段階 ― 承認依存型(相手に委ねすぎるタイプ)
この段階では、自分の存在や価値を「相手にどう見られるか」に強く依存します。
- 価値観の不一致:自分の考えが理解されないことを「自分そのものを否定された」と感じやすい。
- 役割期待のズレ:「夫(妻)ならこうあるべき」という役割と自己評価が直結し、認められないと強い不満につながる。
- 感情処理の違い:相手に嫌われたくなくて感情を抑え込み、後から爆発したり再燃する。
👉 この段階では、「分かってくれない!」と爆発するか、溜め込んで再燃するか、いずれにせよ喧嘩がループしやすいのです。
👉 このように、表面的には同じ「価値観・役割・感情処理」の違いに見える喧嘩も、実際には発達段階ごとの構造的な特徴によって形を変えます。しかし、段階の違いだけでは「なぜ繰り返されるのか」を十分に説明できません。次に、繰り返しを生み出す“心理的ループ”を見ていきましょう。
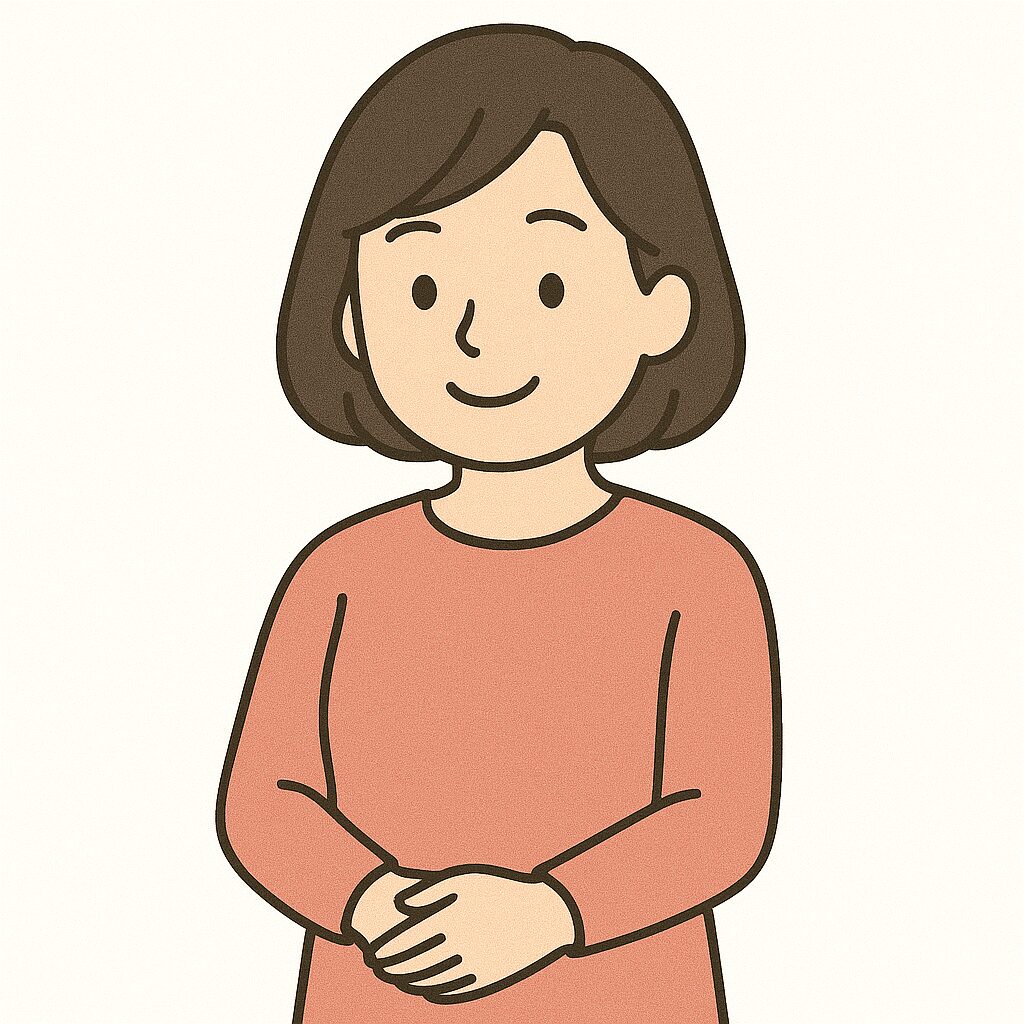
段階によって喧嘩のパターンが全然違うんですね。
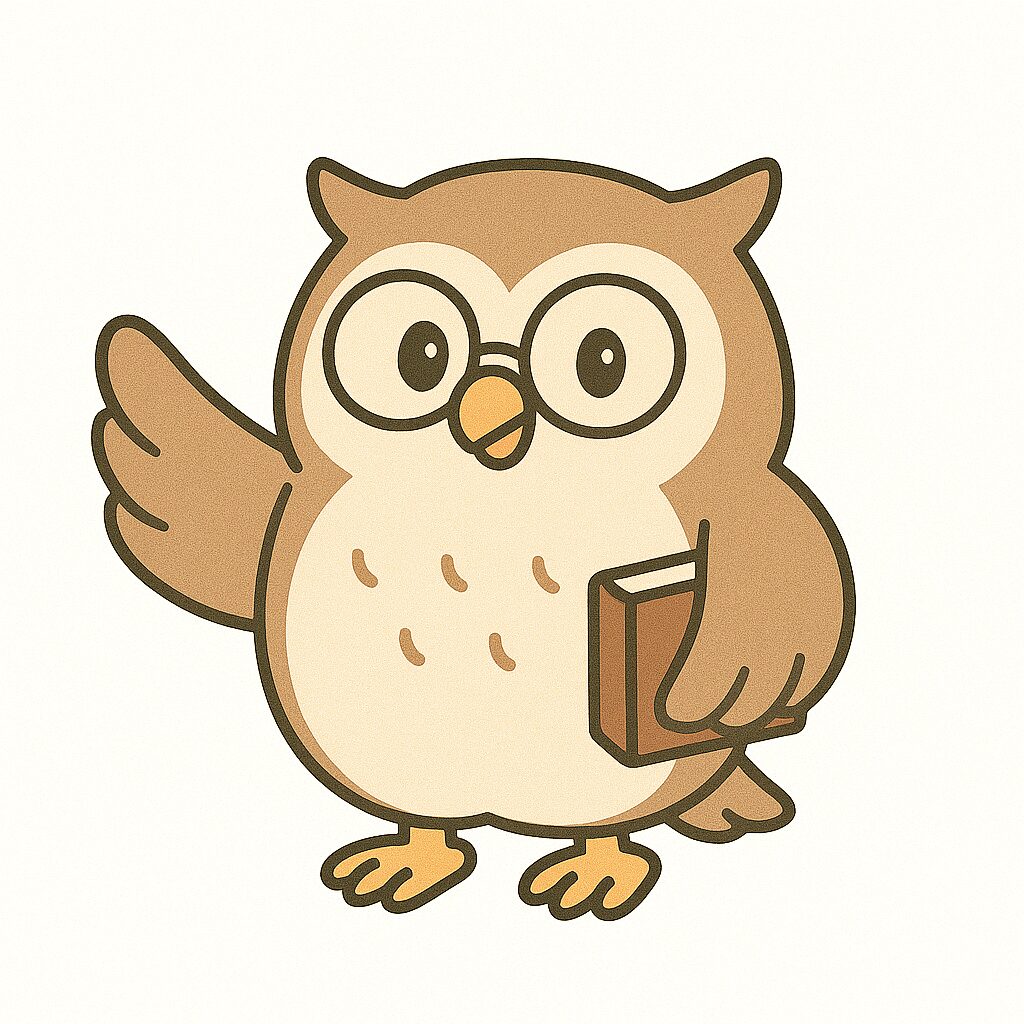
そうなんです。ただ、段階の違いだけでなく、心の中で繰り返される“心理的なループ”も喧嘩を再生産してしまうんです。
🍀 繰り返す喧嘩を生み出す心理的ループ
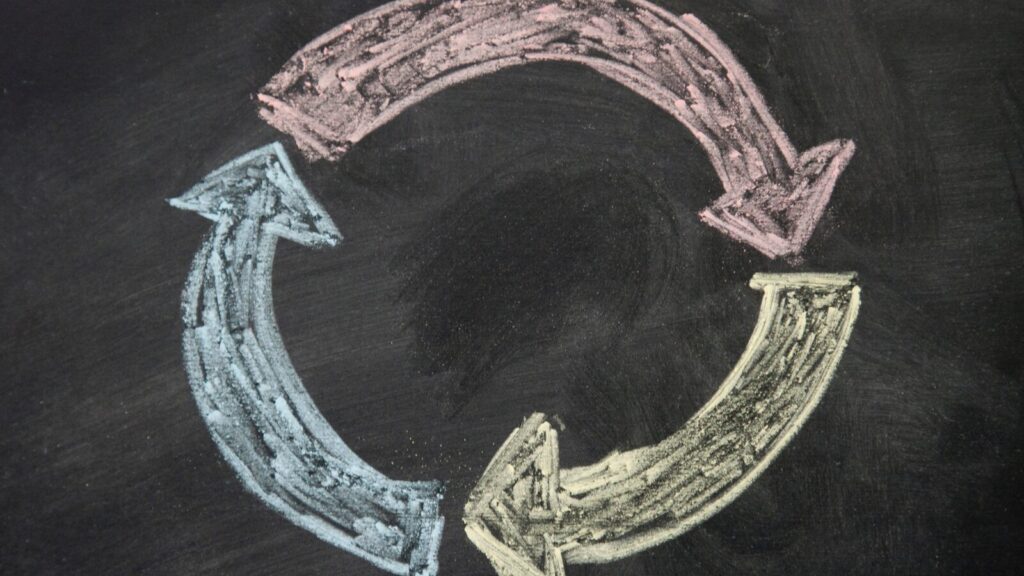
夫婦喧嘩は一度解決したように見えても、なぜか同じテーマで再燃してしまうことがあります。そこには、心理的な「ループ」が大きく関わっています。
1. 投影と反応の連鎖
自分の中にある不満や怒りを直視できず、「相手が自分を軽視している」と思い込んでしまうことがあります。これは心理学でいう投影という働きで、自分の感情を相手に貼り付けてしまう状態です。
たとえば「本当は自分が家事の分担に不満を持っている」のに、「相手は自分を大事にしていない」とすり替わり、攻撃的な言葉を投げてしまう。すると相手も防御反応をとり、結果として衝突が連鎖的に続いてしまいます。
2. 未解決の感情の再燃
喧嘩の火種は、そのときの出来事だけではありません。多くの場合、根っこには幼少期の親への怒りや悲しみが横たわっています。「どうせ分かってもらえない」「話しても聞いてもらえない」という体験が、夫婦関係の中で再び刺激され、古い感情がよみがえるのです。
こうなると、目の前の夫婦喧嘩は「今のテーマ」だけでなく、過去から積み残された感情も同時にぶつかるため、繰り返されやすくなります。程度によっては、外部のカウンセラーや専門的支援を利用することも有効です。セルフケア → 夫婦での対話 → 必要なら専門家、という段階的な対応が現実的です。
3. 感情処理スタイルの違いによるすれ違い
ある人は「感情をすぐに言葉にしてすっきりしたい」と考え、別の人は「時間をかけて整理してから話したい」と思います。この違いが「逃げている」「しつこい」といった誤解を生み、対立を強めてしまいます。
本来はスタイルの違いにすぎないのに、互いに「自分を理解してくれない」と受け止めてしまい、同じやり取りが繰り返されるのです。
4. 相手像の固定化
「どうせまたこうなる」「相手はいつも同じことを言う」といった思い込みが強まると、相手を新しい目で見ることが難しくなります。その結果、対話の余地がなくなり、「いつものパターン」に引きずられて喧嘩が再生産されてしまうのです。
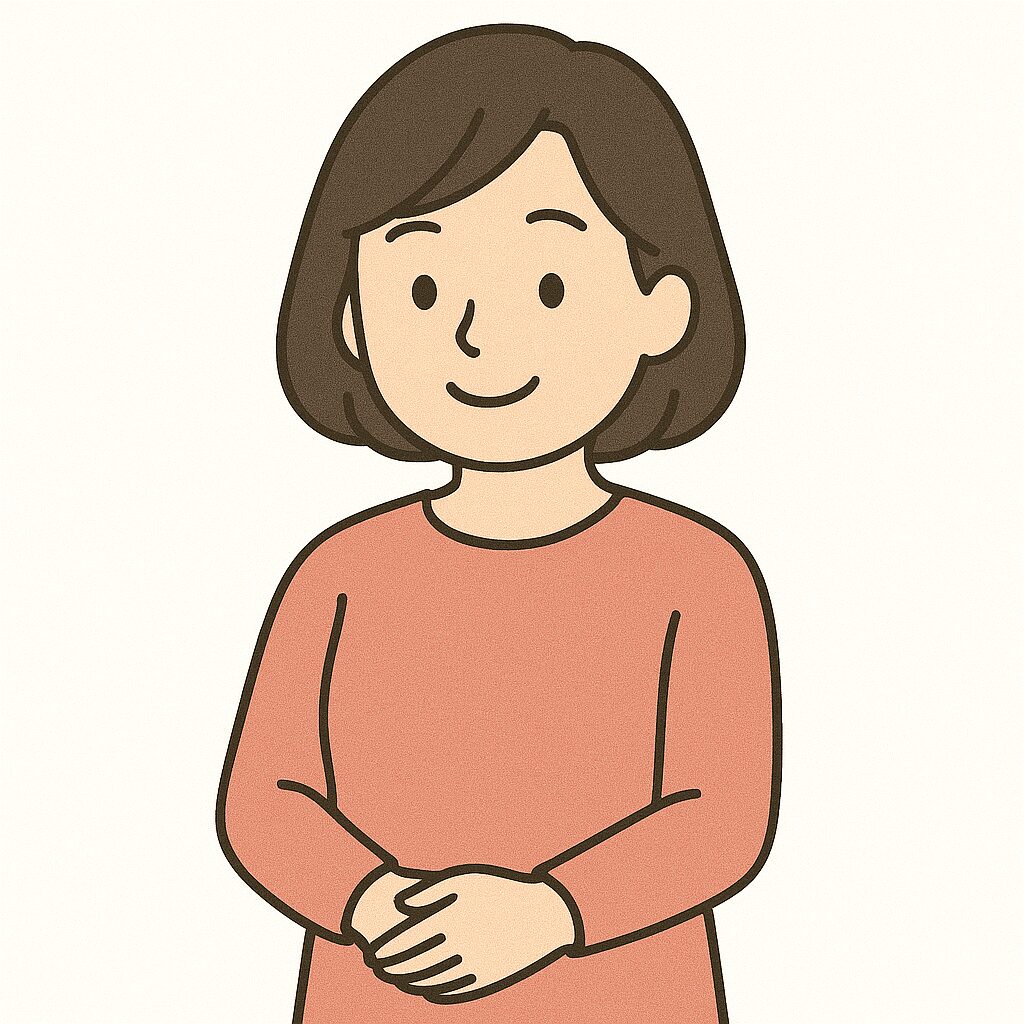
なるほど…喧嘩が繰り返されるのは、心理的なループも影響しているんですね
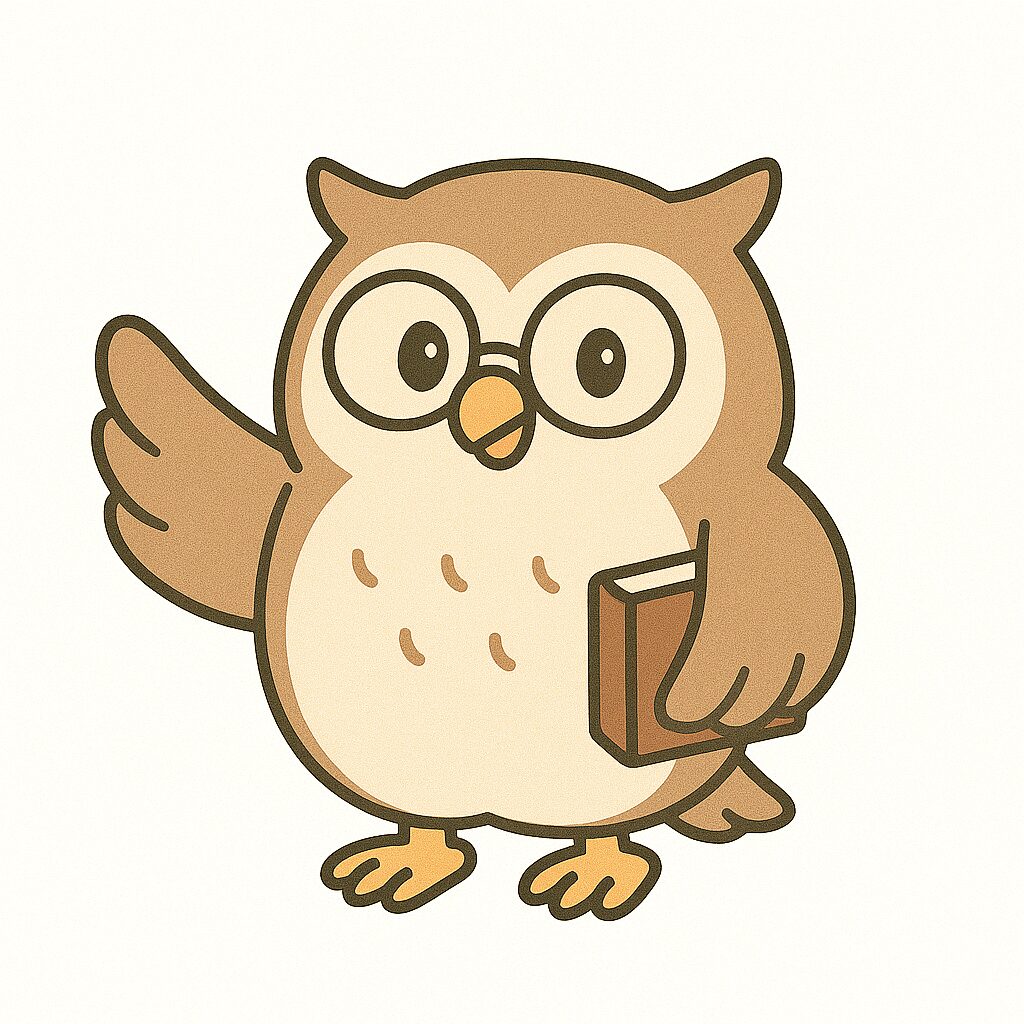
その通りです。でも安心してください。ループは工夫次第で断ち切れます。次はその具体的な方法を見ていきましょう。
🍀 ループを断ち切るための実践法
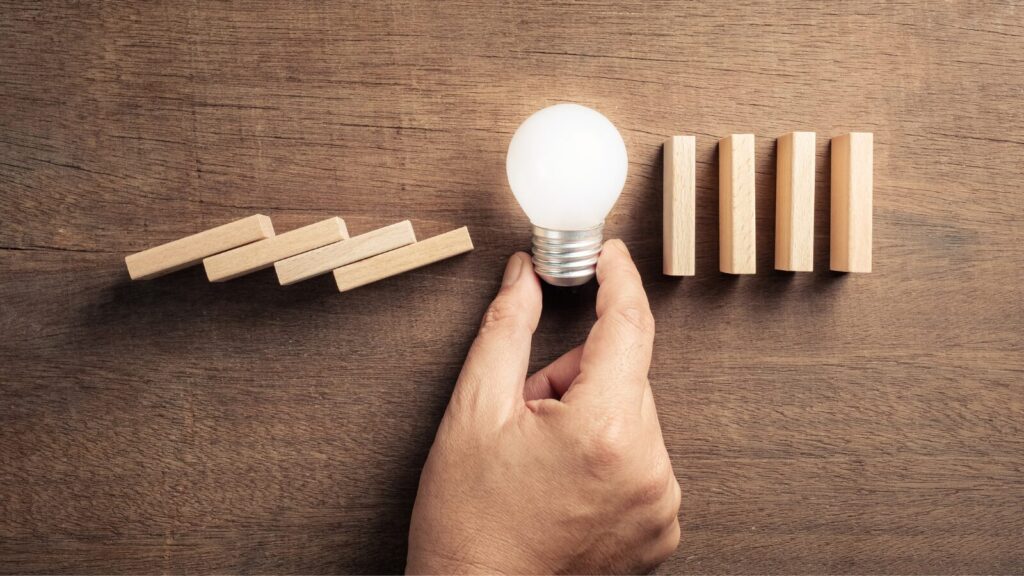
夫婦喧嘩を減らすには、「冷静に話そう」だけでは解決できません。大切なのは、相手の発達段階を見極めて、その段階に合わせた関わり方を選ぶことです。そうすることで、繰り返される心理的ループを断ち切る糸口が生まれます。
第二段階の相手には…
第二段階の人は「自分の欲求や損得」を最優先にするため、正しさや感情的な訴えかけは届きにくい傾向があります。
- 実生活の例:「どうして手伝ってくれないの!」と責めるより、「これを一緒にやってくれると、あなたの自由な時間も増えるよ」と伝えるほうが、相手に響きやすい。
- 心理ループとの関係:投影や怒りの爆発に対しては、感情で押し返すより「損得の枠組み」に切り替えることで、連鎖を止めやすくなる。
👉 ポイント:「正しいことを納得させる」よりも「得になる形で提案する」。
第三段階の相手には…
第三段階の人は「相手にどう見られているか」が自己評価に直結しています。そのため、話し合いの前に安心感や承認を与えることが大切です。
- 実生活の例:「最近あなたが家のことを頑張ってくれているのは分かってる。だからこそ、少しだけ分担を見直せないかな?」と伝えると、反発ではなく「理解してくれている」という感覚から対話に入りやすい。
- 心理ループとの関係:「分かってもらえない」という感覚が未解決の感情を再燃させやすい段階なので、まず承認を示すことでループを断ち切る効果がある。
👉 ポイント:「正論で説得する」のではなく「気持ちを理解する姿勢」を先に示す。
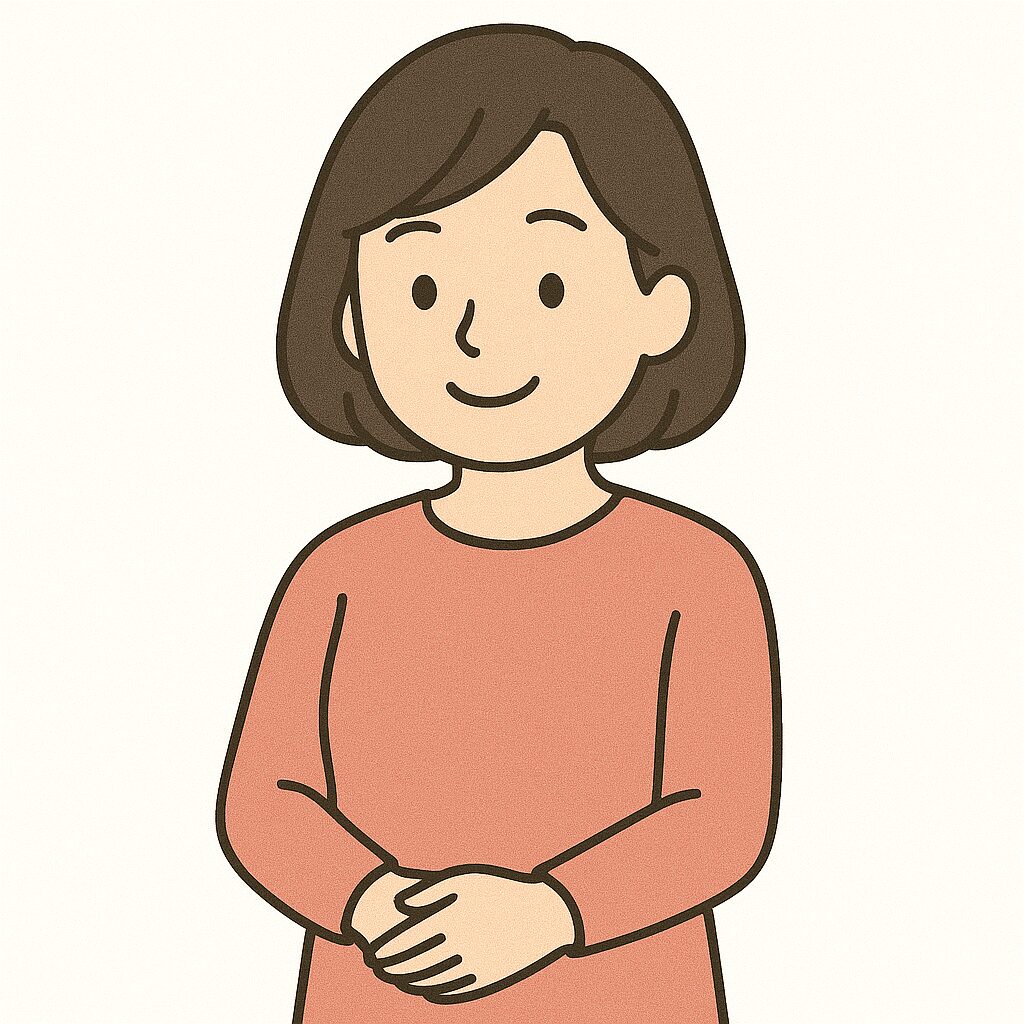
相手の段階に合わせて対応するのが大事なんですね。
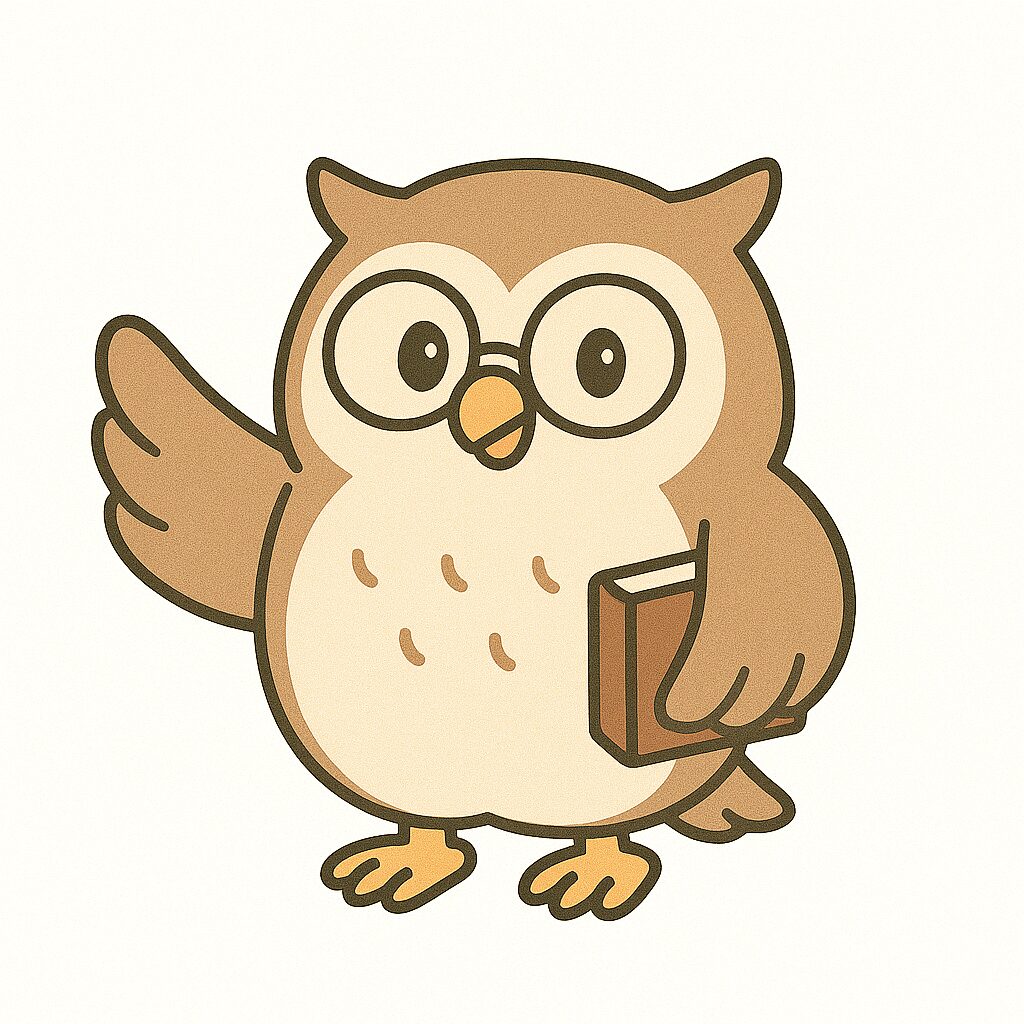
ええ。そして『誰にでも効く正解はない』ことを理解するのが第一歩です。最後に全体を整理してまとめましょう。
🍀 まとめ
夫婦喧嘩が繰り返される理由は、単なる「性格の不一致」ではありません。
- 表面的には「価値観・役割期待・感情処理の違い」
- 背後には「発達段階の構造的な特徴」
- さらに深層には「心理的なループ」
こうした多層的な要因が絡み合っているのです。繰り返しのループを断ち切るには、相手の段階を理解し、それに合ったアプローチを取ることが欠かせません。「なぜ同じ喧嘩が起きるのか」を知り、「相手に届く伝え方」を工夫することこそ、夫婦関係を前に進める現実的なカギなのです。




